この記事は、2018年10月29日に更新しました。
昨今のCTやMRIといった画像診断技術の発達には、めざましいものがあります。
CTやMRIの診断能は高く、現在の神経疾患の診断において必須の検査となっています。
画像検査は、疾患の原因が視覚化されるために患者さんへの説得力があり、病状説明においても威力を発揮します。
ですが、これらの画像診断は本来は補助診断に過ぎません。
神経学的所見が裏付けされてこそ、神経疾患の診断に到達できるのです。
極端な例えですが、左の手足の運動麻痺が主徴候の症例に対して、左内包後脚で陳旧性のラクナ梗塞像が見つかったとしても、いま解決するべき症候とは無関係ですよね。
神経内科医のかっこいいところは、消化器内科医が内視鏡を、循環器内科医がカテーテルといったマシーンを抱えて戦いに挑む中、神経内科医は老練な徒手拳法の達人のごとく、たった一本の打腱器を持って立ち向かっていく姿なのです。
医師個人のスキルに大きく依存する分野であり、非常に勉強しがいのある領域だと思います。
-1. 『ベッドサイドの神経の診かた』
神経徴候の鑑別方法を習得するには、基礎の解剖から覚えなおすのが王道です。
ですが、解剖学の教科書をイチから読み直すのでは効率がよくありません。
一言でいうなら、”単調な暗記作業はつまらない”からです。
実際に出現する徴候、ないし症候と障害部位を符号させながら覚えていく方が、モチベーションを保てます。
たとえば、
「ロンベルク徴候とは、閉眼して直立して倒れるかどうか」
↓
「目を閉じるということは、視覚情報を遮断してみるということ。
つまり、ロンベルク試験とは、視覚の修飾を除いて、位置覚障害があるかどうかを調べる検査である」
↓
「位置覚を担当するのは、脊髄後索。この部位が障害される疾患は、脊髄癆やニューロパチーなど」
・・・というように、症候と解剖を有機的に関連づけた方が覚えやすいのではないかと思います。
(※余談ですが、位置覚も視覚も遮断されると、自分の平衡感覚がゼロになります。宇宙空間をただよう感じですから、真のロンベルク陽性症例は倒れこみます。閉眼してちょっとぐらつく、という程度の症例は、厳密にはロンベルク陽性とはいえません。)
臨床の場で、知識を道具として使用していくことがスキル習得の近道でしょう。
よく言いますよね?
「習うより慣れろ」
と。
そんな勉強をしていくうえで、おススメの書籍は、ずばり『ベッドサイドでの神経の診かた』。
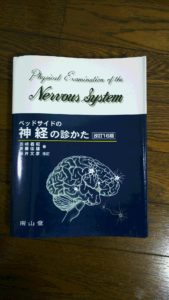
プライマリケアの場で何十年も使うことになる書籍です。
写真は古い版のものですが、次々に改訂を重ね、2018年現在は第18版が販売されています。
本書では、難解なイメージのある神経学的検査を、図をまじえてとても見やすく解説しています。
文章も読みやすく、万人向けの書籍といえるでしょう(ドクターのみならず、理学療法士さんも好んで読まれているそうです)。
タイトルの通り、診察の仕方に重点をおいた臨床医のための実践本です。
-2. 遭遇頻度の高い徴候からおさえていくべし!
本書を使って臨床力を上げていくには、要領が大事です。
それは、臨床でよく遭遇する徴候からおさえていくことです。
神経内科を専門とされるドクターは、日常的に様々な症状の患者さんを診察されていると思いますが、プライマリケアの場では、
「片側の脱力感」
「めまい」
「四肢のしびれ」
を訴える方が非常に多いかと思います。
非専門医であれば、まずは高頻度に遭遇する徴候から確実におさえていきましょう。
(『整形外科徒手検査法』もあわせて読むと、さらに末梢神経障害へのアプローチができるようになります)
「いままでやってきた検査法が、本当はこうやるものだったのか!」
「麻痺を検出する検査法には、他にもこういうものがあった!」
・・・など、即座に臨床に活用できる知識ばかりですから、勉強が苦になりません。
「神経疾患の診断は、理学所見が第一!」 ・・・というのが本章のテーマです。
MRIの偽陰性率は6%、特に小脳などの後方循環系では30%前後といわれていますから、画像検査のみで診断づけることは戒められねばなりません。
ですが、 「画像診断は不要!」 というわけではありません。
たとえば、小脳梗塞では、回内・回外試験などの協調運動が正常となる場合があります。
小脳上部では、構音障害などの小脳性運動失調が出現しやすいのですが、小脳下部ではあまりはっきりしないのです。
体幹失調を精査すれば偽陰性率を下げられますが、 「なんだかふらつく」 と発言される高齢者は非常に多く、非特異的な徴候なので、今一つ決め手にかけます。
理学初見のみでも限界があるのです。
要は、両者とも上手に使いこなして、診断能を上げていくべきということでしょう。
むしろ、CTやMRI技術は客観性と再現性に優れていますから、診断能を底上げできるか否かは、診察医の理学所見の腕前如何にかかっているといっても過言ではないでしょう。
ぜひ、『神経の診かた』を習得してみてください。
(わたし自身が、まだまだ未熟な身なのですが・・・)





